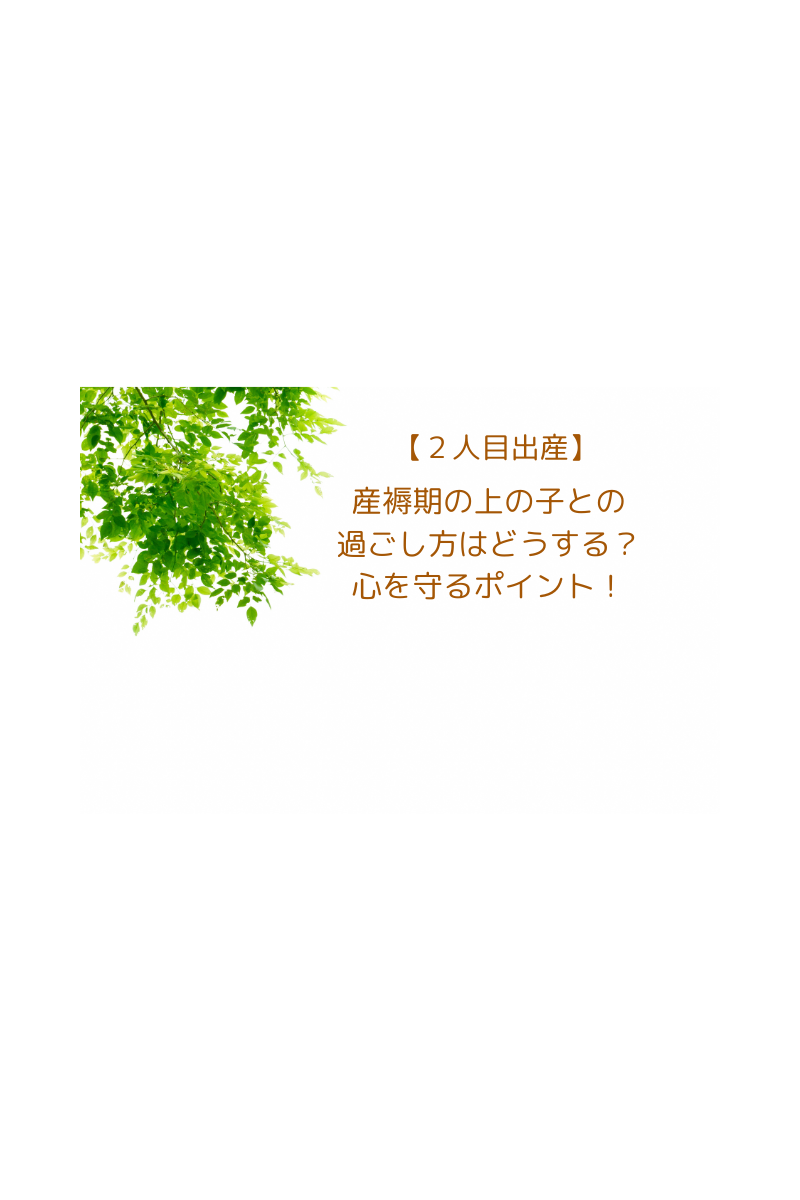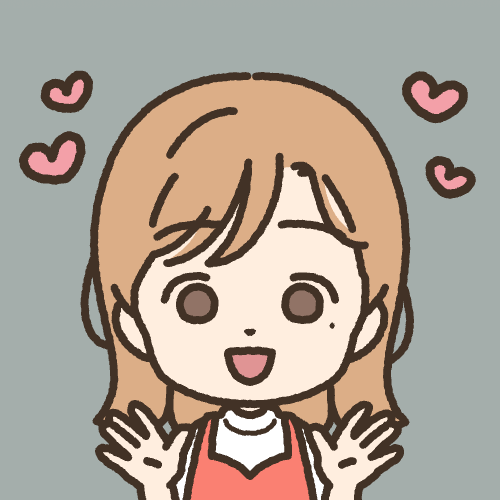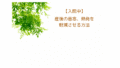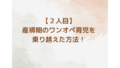産褥期は、母体の回復が最優先の時期ですが、上の子がいるとその子のケアも必要になりますよね。
これから出産予定で上の子との過ごし方や、上の子のメンタルケアなど不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
子供を出産しもうすぐ産後1ヶ月経とうとしている、現在産褥期真っ只中の私が、経験を元にまとめてみました。
産褥期の上の子との過ごし方
産後の上の子の心を守るポイント
不安サインと対処法
2人目出産後、産褥期の上の子との過ごし方
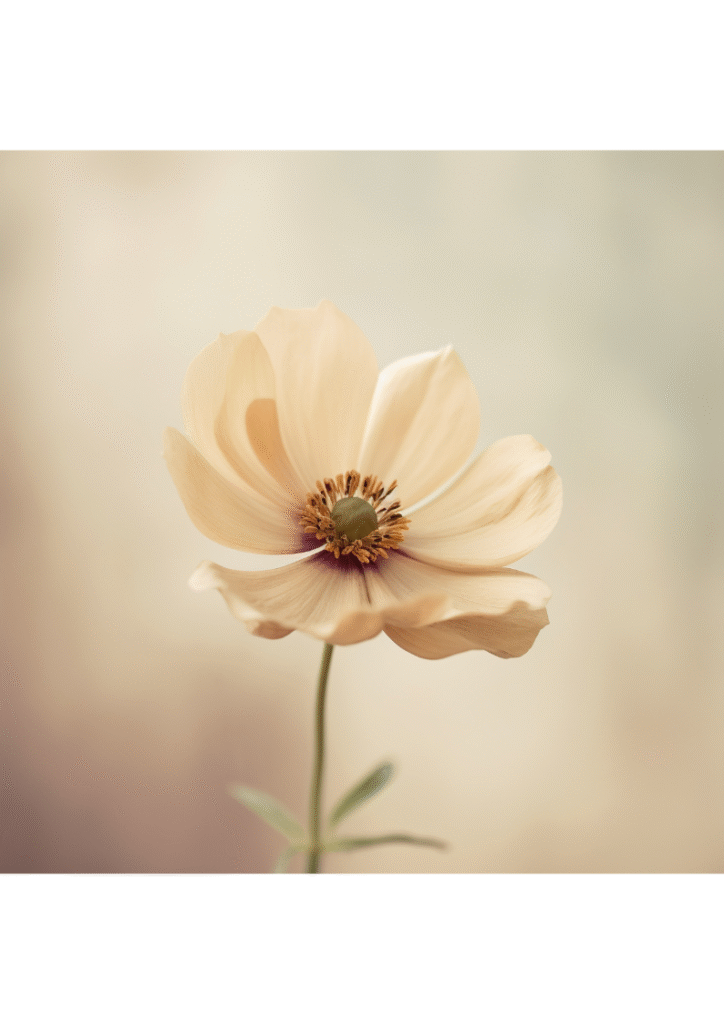
上の子の心のケアを大切にする
赤ちゃん返りを受け止める
甘えたがる、わがままになるなどの行動は自然な反応です。できる限り受け入れてあげましょう。
「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」と上の子に無理に我慢を強いるより「ママの大事な子」や「大好きな⚪︎⚪︎ちゃん」などと伝えて特別感や愛情を言葉で伝えることが大切です。
物理的な関わりを工夫する
添い寝、絵本の読み聞かせ、おしゃべりを中心に関わる
激しい遊びや外出は控えつつ、一緒に布団でゴロゴロしたり、絵本を読んだりすることで愛着を保てます。
私も寝る前に、赤ちゃんは夫にお願いし上の子に絵本の読み聞かせをしています。
お手伝いをお願いして役割を与える
赤ちゃんのおむつを持ってきてもらう、お尻拭きを渡してもらうなど簡単なことでもお願いすることで「ママを助けている」という自信になります。
シャボン玉やボール遊び、滑り台など家の中でできる遊びをする
ベランダでシャボン玉を一緒に吹いたり、ペットボトルをピンに見立てボーリングをしたり、滑り台などがある場合は危なくない範囲で見守ったりして家の中でできる遊びを中心に過ごせるようにしましょう。
サポートを積極的に活用する
夫や家族、自治体のサポートに頼る
家事や上の子の遊びは他の人に任せて、体を休めながら上の子との「質の良い関わり」だけに集中してあげると良いです。
夫が休みの日は、思いっきり外で遊んでもらいましょう。
事前に「何して遊ぶ」か考えていてくれる旦那様ならいいのですが、遊びの内容が決まっていない場合はイベントなどを事前に調べて提案しておくのもありです。
私は夫が休みの日を聞いて「この日はアンパンマンショーがあるよ!」「イルカがいるこの場所に行くのはどうかな?」など夫が悩まないように先回りして提案しました。
一時保育やファミサポも検討
体を休める時間を確保するためにも、行政のサービスを活用するのは有効です。事前に登録などが必要になるので出産前に情報収集をして登録手続きをしておくと良いです。
産後の上の子の心を守るポイント

「あなたが大切」というメッセージを繰り返す
・「赤ちゃんが来ても、あなたはママにとって一番大事な子だよ」と言葉で繰り返し伝える。
・「あなたがいてくれて、ママ本当に助かっているよ」など、存在を肯定する言葉を意識。
甘えを否定しない・抱きしめる
・赤ちゃんがえりは成長の一部。「抱っこ」「できない」などの行動は愛情を確認したいサインです。
・抱っこはできないので可能な範囲で抱きしめたり、「うんうん、そうだよね」と共感を示すと気持ちが落ち着きます。
特別な時間・空間を作る
・1日5分だけでも「ママと2人だけの時間」を作ってあげられると良いです(寝かしつけ前にギュッとする、トントンする、大好きと伝えるなど)
・赤ちゃんのいる場所とは別の「上の子ゾーン」を作ってあげると「自分の世界」が守られ安心感につながります。
上の子の気持ちを言語化して代弁する
「ママが赤ちゃんばかり見ていると、ちょっと寂しいね」「もっと遊びたかったんだね」など、自分の気持ちをわかってくれてると感じさせることが重要です。
不安サインと対処法
| よくある行動 | 上の子の気持ち | 対処法 |
| 赤ちゃんを叩く/嫌がる | 注目されたい・やきもち | 「ママに赤ちゃんよりかまってほしい」サインとして受け止め、まず上の子を抱きしめてから注意する |
| 癇癪 | 不安や寂しさの発散 | 「今は辛い気持ちなんだね」と共感し、落ち着いてから話す |
| 食欲減退・睡眠変化 | 心の混乱 | 無理に食べさせず、できるだけリズムを整えて安心できる環境を作る |
まとめ
子供が1人の時と違い、自分自身もなかなか余裕が持てないことが増えたように感じます。
まずは自分に余裕ができないと子供に優しく接することができません。
自分の余裕を作るためにも、頼れる人やものは頼るべきだと思います。
あと下の子が寝ている時間は、上の子に関わる絶好のチャンスです。私はその時間しつこいくらいに話しかけたり、抱きしめたりしていました。
上の子が可愛くない症候群というものがあるらしく、心配していましたが幸いにも今のところそれはなく、なるべく上の子に「大好き」や「宝物の⚪︎⚪︎ちゃん」と伝えています。
子供のメンタルも大事ですが、一番大切なのは自分自身のメンタルだと思います。
自分自身の体調やメンタルを整えて産褥期乗り越えてくださいね。